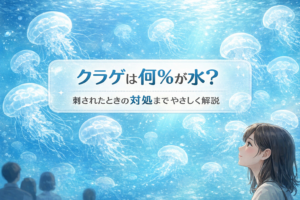タコの豆知識、知りたいのはどんなこと?
「タコって心臓が3つあるって本当?」「脳みそが9個もあるって聞いたけど…」このような驚きの雑学を耳にして、もっと詳しく知りたいと思ったことはありませんか。タコは私たち人間とはまったく異なる進化を遂げた生き物で、その生態には想像を超える面白い特徴が数多く隠されています。小学生の自由研究から大人の飲み会まで、会話が一気に盛り上がるタコの不思議な世界を一緒に探ってみましょう。この記事を読めば、誰かに話したくなる驚きの発見がきっと見つかります。
「心臓が3つ?脳が9つ?」聞いたことはあるけど本当か確かめたい
インターネットやテレビで「タコには心臓が3つある」「脳が9つもある」という情報を見かけたことがある方は多いでしょう。しかし、これらは本当なのか、それとも誇張された話なのか、確信が持てないまま気になっている人も少なくありません。実際のところ、タコには3つの心臓が存在し、2つは各エラに血液を送るため、残り1つは全身に血液を循環させるために働いています。脳については、中央に1つの主要な脳があり、8本の腕それぞれに神経節が分散しているため「9つの脳」と表現されることがあるのです。
これらの身体構造は、タコが海という環境で生き抜くために進化させた驚異的なシステムです。興味深いことに、タコが泳ぐときには全身用の心臓が一時的に止まってしまうため、長距離の遊泳よりも海底を這って移動することを好みます。こうした具体的な仕組みを知ることで、単なる雑学以上の深い理解が得られ、子どもからの質問にも自信を持って答えられるようになるでしょう。
子どもの「なんで?」に自信を持って答えられるようになりたい
子どもは水族館でタコを見たり、食卓でタコ料理を食べたりする際に、次々と疑問を投げかけてきます。「タコの足は何本?」「どうやって色が変わるの?」「なんで吸盤がついてるの?」といった質問に対して、曖昧な答えしか返せないと感じている親御さんは多いのではないでしょうか。子どもの好奇心に応えることは、学習意欲を高め、親子のコミュニケーションを深める絶好の機会です。
タコの基本的な生態を理解しておけば、こうした質問にも的確に答えられます。例えば、タコの8本の腕にはそれぞれ約300個の吸盤があり、これらは単なる吸着装置ではなく、味覚と触覚を同時に感じ取れる高度なセンサーとして機能しています。また、体色を変える能力は、皮膚にある色素胞という特殊な細胞が脳からの指令で瞬時に変化することで実現しています。こうした科学的な知識を持つことで、子どもの「なんで?」に自信を持って答えられる親になれるのです。
この記事で得られる、科学的根拠のあるタコの驚きの生態
この記事では、単なる面白い雑学だけでなく、最新の科学研究に基づいたタコの生態について詳しく解説します。2024年から2025年にかけて発表された研究では、タコが貝殻を組み合わせて移動式の隠れ家を作る行動や、迷路を記憶して最短ルートを見つける学習能力が確認されています。また、タコが真水で即死してしまう理由についても、浸透圧の変化による科学的なメカニズムが明らかになっています。
さらに、タコの求愛行動や繁殖における興味深い生態、擬態能力の精密な仕組み、そして「タコが自分の足を食べる」という現象の真相まで、幅広いテーマを取り上げます。これらの知識は、自由研究のテーマ選びや、飲み会での話題提供、さらには料理を楽しむ際の新たな視点として活用できるでしょう。科学的根拠に基づいた正確な情報を身につけることで、あなたの会話はより魅力的で信頼性のあるものになります。
タコの魅力を「ただの海の生き物」で終わらせていませんか?

多くの人にとって、タコは「たこ焼きの材料」「水族館で見かける面白い形の生き物」という程度の認識かもしれません。しかし、タコを単なる食材や観賞対象として見ているだけでは、その驚異的な能力や知能の高さを見逃していることになります。現代の科学研究によって、タコは無脊椎動物の中でも極めて高い知能を持ち、道具を使いこなし、問題を解決する能力があることが明らかになっています。タコの真の魅力を知ることで、日常の会話や子どもとの対話がより豊かになるだけでなく、生き物の進化や生態系への理解も深まるのです。
料理としてしか見ていないと、驚異的な能力を見逃している
日本は世界のタコ消費量の約6割を占めるタコ大国で、たこ焼きや酢ダコ、タコ刺しなど、様々な料理で親しまれています。しかし、食材としての側面ばかりに注目していると、生き物としてのタコが持つ驚異的な能力を見逃してしまいます。例えば、タコの血液が青いことをご存知でしょうか。これは酸素を運ぶ際に鉄ではなく銅を使用するヘモシアニンという物質が含まれているためで、酸素濃度の低い深海でも効率的に呼吸できる仕組みなのです。
また、タコは道具を使う数少ない無脊椎動物として知られています。野生のタコがココナッツの殻を持ち運んで隠れ家として使ったり、石を積み上げて巣の入り口を塞いだりする行動が観察されています。水族館では、タコが瓶の蓋を器用に開けたり、脱出するために水槽の隙間を見つけ出したりするエピソードも報告されています。料理として美味しく食べることも大切ですが、その背後にある生き物としての知能や能力を知ることで、タコへの敬意と興味が深まるはずです。
イカとタコの違いを子どもに聞かれて答えられなかった経験
「タコとイカって何が違うの?」という子どもからの素朴な質問に、明確に答えられなかった経験はありませんか。両者は同じ軟体動物で見た目も似ているため、混同されがちですが、実際には明確な違いがあります。最も分かりやすいのは腕の数で、タコは8本、イカは10本(8本の腕と2本の長い触腕)です。また、イカには体内に軟骨質の骨格(甲)があるのに対し、タコは完全に骨のない軟体構造をしています。
生息環境や生態にも大きな違いがあります。タコは主に海底の岩場や穴に隠れて生活し、単独行動を好む生き物です。一方、イカは水中を群れで泳ぎ回ることが多く、より活発な遊泳生活を送っています。擬態能力についても、タコは周囲の環境に合わせて体色だけでなく皮膚の質感まで変化させる高度なカモフラージュ能力を持っていますが、イカの擬態能力はそれほど複雑ではありません。こうした違いを理解しておくことで、水族館での観察がより楽しくなり、子どもの質問にも自信を持って答えられるようになります。
古い情報のまま話すと、最新の研究成果を知る人には恥ずかしいことも
タコに関する研究は日々進歩しており、10年前の常識が今では更新されているケースも少なくありません。例えば、以前は「タコには感情がない」と考えられていましたが、最近の研究では、タコがストレスや不安を感じ、それに応じて行動を変化させることが確認されています。特に「タコが自分の足を食べる」という自食行動は、単なる空腹ではなく、環境的ストレスや刺激不足による心理的な問題が原因であることが明らかになっています。
また、タコの知能に関する理解も大きく進んでいます。2024年から2025年にかけての研究では、タコが未来を予測して行動を計画する能力や、人間の顔を識別して記憶する能力が報告されています。水族館のスタッフの中には、特定のタコに覚えられて、近づくたびに異なる反応を示されるという体験をする人もいるほどです。こうした最新の研究成果を知らずに古い情報でタコについて語ると、詳しい人からは「それは昔の説ですよ」と指摘されてしまう可能性があります。常に新しい情報をアップデートすることが大切です。
なぜタコはこれほど注目される生き物になったのか?
タコが多くの人を魅了するのは、その驚異的な身体構造と知能の高さにあります。心臓を3つ持ち、脳みそが9つもあるという生き物は、地球上でもタコだけです。日本では古くから料理として親しまれてきましたが、最近の科学研究により、道具を使いこなし学習能力を持つ高知能動物としての側面が注目されています。この記事を読めば、子どもとの会話や飲み会での雑談で使える驚きの豆知識を手に入れることができるでしょう。
心臓3つ、脳みそ9つ――進化が生んだ独自の身体システム
タコの身体構造は、他の生き物と比較しても極めて特殊な進化を遂げています。3つの心臓のうち、2つは鰓心臓として血液を鰓に送り、残り1つの体心臓が全身に血液を循環させる仕組みです。この複雑なシステムが必要な理由は、タコの血液が人間と異なり、銅を含むヘモシアニンで酸素を運ぶためです。この青い血液は、酸素濃度の低い深海環境でも効率的に機能するよう進化したものですが、その代償として複数の心臓が必要になったのです。
脳の構造も独特で、中枢となる脳は頭部にありますが、8本の腕それぞれに独立した神経節が存在します。この分散型の神経システムにより、各腕が独自に判断を下すことができ、切り離された腕でも一定時間は動き続けることが知られています。実際、タコの神経細胞の約60%は腕に分布しており、中央の脳は全体の方向性を決定し、各腕は細かい動作を自律的に制御しているのです。この「9つの脳」システムは、複雑な環境で素早く反応し、複数の作業を同時に行うために進化した、タコ特有の生存戦略といえるでしょう。
道具を使い、問題を解決する――無脊椎動物とは思えない知能
タコの知能の高さを示す最も印象的な証拠は、道具の使用能力です。インドネシア近海で観察されたタコは、ココナッツの殻を2つ組み合わせて持ち運び、必要に応じて組み立てて隠れ家として使用していました。この行動は、単なる本能ではなく、将来の必要性を予測して行動する計画性を示しています。また、水族館では、タコが瓶の蓋を回して開けたり、配管の構造を理解して水槽から脱出したりする事例が報告されており、その問題解決能力の高さが証明されています。
学習能力についても、タコは迷路を記憶して最短ルートを見つけることができ、一度学習した内容を長期間保持することが確認されています。さらに興味深いのは、タコが観察学習を行うことです。他のタコが特定の課題を解決する様子を見て、自分も同じ方法を試すという行動が実験で確認されており、これは高度な認知能力を必要とします。無脊椎動物でありながら、タコは脊椎動物に匹敵する、あるいはそれを超える知能を持つ生き物として、神経科学や認知科学の分野で熱心に研究されているのです。
日本の食文化から最先端科学まで、タコ研究の新たな可能性
日本は世界最大のタコ消費国であり、タコは日常的な食材として文化に深く根ざしています。しかし近年、タコの高い知能が明らかになったことで、単なる食材以上の存在として再評価されています。多くの研究機関では、タコの分散型神経システムを人工知能やロボット工学に応用する研究が進められており、日本の伝統的なタコ文化が最先端科学技術の発展に貢献する可能性が期待されています。
特に注目されているのは、タコの腕の自律制御メカニズムです。各腕が独立して動作しながらも全体として協調する仕組みは、複雑な環境で作業するロボットアームの設計に応用できると考えられています。また、タコの擬態能力を模倣した新素材の開発や、吸盤の吸着メカニズムを応用した医療機器の研究も進んでいます。日本の豊富なタコ文化と科学研究の融合により、新たな技術革新が生まれる可能性は十分にあるのです。子どもたちにとっても、身近な食材が最先端科学の研究対象になっているという事実は、科学への興味を引き出す絶好の話題となるでしょう。
今すぐ使えるタコの豆知識、シーン別に紹介
タコは海の中でも特に神秘的な生き物として多くの人に愛されています。心臓が3つもあることや、9つの脳を持つという驚きの生態から、真水に触れると即死してしまう理由まで、タコには知れば知るほど面白い特徴が満載です。この章では、子どもの自由研究や大人の会話のネタとして使える、科学的根拠に基づいたタコの雑学を詳しく解説します。水族館での観察がより楽しくなる基本的な生態から、最新の研究で明らかになった高い知能まで、今すぐ使える豆知識をお届けします。
「真水で即死するのはなぜ?」子どもの疑問に答える基本生態
子どもから「タコは真水で死んじゃうの?」と聞かれたとき、科学的に正確な説明ができるでしょうか。タコが真水で即死してしまう理由は、浸透圧の違いにあります。タコの体液は海水とほぼ同じ塩分濃度(約3%)に調整されているため、塩分のない真水に入ると、細胞膜を通じて大量の水が細胞内に流入します。その結果、細胞が膨張して破裂し、心臓や脳などの重要な器官が機能を失って死に至るのです。この現象は浸透圧ショックと呼ばれ、海水魚全般に共通する生理学的特性です。
興味深いことに、この特性は料理にも関係しています。生きたタコを処理する際には、真水ではなく海水か塩水を使う必要があります。また、タコの寿命は意外と短く、多くの種類が1~2年程度しか生きません。これは成長が早く、繁殖後に死んでしまう生態と関係しています。メスは産卵後、卵が孵化するまでの約2ヶ月間、一切食事を取らずに卵を守り続け、孵化を見届けた後に力尽きてしまいます。オスも交尾後まもなく死んでしまうことが多く、まさに命をかけた子育てを行う生き物なのです。こうした科学的な説明は、子どもの好奇心を満たすだけでなく、生命の尊さを伝える良い機会にもなります。
擬態能力と吸盤の秘密――水族館で観察したくなる能力の仕組み
タコの擬態能力は、生き物の中でも群を抜いて優秀です。わずか0.3秒で体の色や模様を変化させることができ、岩、海藻、砂地など、周囲の環境に完璧に溶け込むことができます。この驚異的な能力は、皮膚に存在する色素胞という特殊な細胞によって実現されています。色素胞は脳からの指令を受けて瞬時に収縮・拡張し、赤、黄、茶、黒などの色素を表面に現したり隠したりします。さらに、皮膚の表面にある筋肉を使って突起を作り出すことで、質感まで変化させることができるのです。
タコの8本の腕についている吸盤も、単なる吸着装置ではありません。1本の腕に約300個の吸盤があり、それぞれが独立して動作し、味覚と触覚の両方を感じ取ることができます。吸盤の内部には化学受容体があり、触れた物質の味を識別できるため、目で見なくても食べられるものかどうかを判断できます。吸着力も非常に強く、体重の数倍もの重さを支えることが可能です。水族館でタコを観察する際は、この擬態能力や吸盤の動きに注目してみてください。色がどのように変化するか、吸盤がどのように使われているかを観察することで、タコの驚異的な能力をより深く理解できるでしょう。
オスとメスで味が違う?料理の場で盛り上がる生態の話
タコ料理を楽しむ際に知っておきたいのが、オスとメスの生態的違いがもたらす味の特徴です。メスのタコは産卵期になると卵に栄養を集中させるため、身の味が淡白になる傾向があります。一方、オスは交尾のために体力を蓄えているため、筋肉質で旨味が強く、身が引き締まっているとされています。日本の料理人は古くからこの違いを理解し、季節や用途に応じてオスとメスを使い分けてきました。
オスとメスの見分け方は、8本の腕の特徴にあります。オスの腕のうち1本は「ヘクトコチルス」と呼ばれる交接腕で、他の腕よりも短く太くなっています。この特殊な腕を使ってメスに精子の入ったカプセルを渡すのですが、この腕は交尾後に切り離されてしまいます。また、タコのおいしさには生息環境も大きく影響します。岩場の多い海域で育ったタコは、餌となる貝類やカニを捕食するために吸盤をよく使うため、身が引き締まって美味しくなります。タコの調理法として「もみ洗い」が重要なのは、表面のぬめりを取り除くだけでなく、筋繊維を柔らかくする効果があるためです。食事の際にこうした豆知識を共有すれば、料理がより一層おいしく感じられ、会話も盛り上がることでしょう。
場面で使い分ける、タコ雑学の効果的な伝え方

タコの豆知識は、自由研究から大人の雑談まで幅広いシーンで活用できる魅力的な話題です。子どもの学習サポートでは、マダコの生息地や求愛行動といった生態的な観点から科学的興味を引き出せます。また、飲み会などの大人の会話では「タコが寂しいと発狂する」といった真偽のほどが気になる雑学が盛り上がりのきっかけになるでしょう。さらに、料理好きの方には、オスとメスの生態的違いがおいしさに関わる秘密として興味深い話題となります。この章では、それぞれのシーンに適したタコの豆知識を紹介し、知識を会話のネタや学習に効果的に活用する方法を解説します。
自由研究向け:マダコの生息地から求愛行動までの観察ポイント
自由研究や授業でタコを扱う場合、日本近海に多く生息するマダコの生態を中心に据えると、身近で興味深い観察記事が作成できます。マダコは水深20~200メートルの岩礁地帯を好み、夜行性で昼間は岩の隙間に身を潜めています。体長は約60センチメートル、体重は3~5キログラムほどで、日本の沿岸では最も一般的なタコの種類です。自由研究では、マダコの生息環境、食性、天敵などをテーマにすると、生態系全体への理解も深まります。
求愛行動の観察も興味深いテーマです。オスがメスに近づく際には、体色を鮮やかに変化させて求愛のサインを送ります。その後、ヘクトコチルスと呼ばれる特殊な腕を使って、精子の入ったカプセルをメスの体内に渡します。この交接腕は交尾後に切り離されてしまい、オスは多くの場合まもなく死んでしまいます。メスも産卵後は卵を守りながら絶食を続け、孵化を見届けた後に生涯を終えます。こうした命をかけた繁殖行動を研究テーマにすることで、生命の神秘や生物の生存戦略について深く学ぶことができます。図書館の図鑑や科学雑誌を活用し、イラストや写真を交えてまとめると、視覚的にも分かりやすい研究資料になるでしょう。
飲み会ネタ向け:「タコは寂しいと発狂する」の真相を科学的に解説
「タコは寂しいと発狂する」という話は、飲み会などで盛り上がる話題ですが、実は科学的根拠に基づいた興味深い現象です。タコは基本的に単独行動を好む生き物で、「寂しさ」という感情を人間と同じように持つわけではありません。しかし、環境的ストレスや刺激不足により異常行動を起こすことが知られています。特に水族館などの限られた環境では、退屈や欲求不満から自分の腕を食べる「自食行動」を示すことがあります。これは環境エンリッチメント(環境の豊かさ)が不足している場合に見られる行動で、ストレス反応の一種と考えられています。
雑談で盛り上がるタコの話題は他にもあります。例えば、タコの血液が青いことや、2つの鰓心臓と1つの体心臓を持つことは、多くの人が驚く事実です。酸素運搬にヘモグロビンではなく銅を含むヘモシアニンを使用するため、血液が青色になるのです。また、タコは道具を使う高い知能を持つ生き物として2025年現在も研究が続けられており、ココナッツの殻を持ち運んで隠れ家にする行動や、瓶の蓋を開ける能力などが確認されています。「タコが自分の足を食べる」ということわざの由来も、この自食行動から来ていると考えられており、古くから観察されていた現象だったのです。これらの豆知識は、料理の席でタコについて語る際にも、科学的な興味深さを添える話題として活用できます。
家族の食卓向け:タコイラストや図鑑を使った楽しい学びの時間
家族での食事や団らんの時間に、タコの豆知識を共有することで、楽しく学べる機会を作ることができます。タコイラストや図鑑を使った説明は、特に小学生から中学生の子どもたちの理解を深めるのに効果的です。例えば、タコの吸盤の構造や心臓が3つあることを説明する際、図鑑のイラストを指差しながら話すことで、複雑な生態も分かりやすく伝えることができます。また、マダコやミズダコ、イイダコなど、種類による違いを図鑑で比較しながら紹介すると、聞き手の記憶により深く残る説明となります。
食卓でタコ料理が出た際には、「このタコの腕には約300個の吸盤があって、それぞれが味を感じられるんだよ」と話しかけると、子どもたちは興味津々になるでしょう。タコの吸盤が味覚センサーとしても機能していることを知ると、食べ物への関心も高まります。また、「タコは頭がいい生き物で、迷路を覚えたり、人の顔を区別したりできるんだ」と伝えることで、単なる食材ではなく、知能を持った生き物として尊重する気持ちも育まれます。図鑑には日本の沿岸に生息するタコの種類や分布も詳しく載っているため、「私たちが食べているこのタコは、どこの海で獲れたものかな」といった会話へと発展させることもできます。視覚的な資料を活用しながら、科学的な知識と食への感謝の気持ちを同時に伝えることで、家族の食卓がより豊かな学びの場になるのです。
タコの豆知識で、あなたの会話がもっと豊かになる
これまでタコの驚くべき生態や知能について多くの雑学を紹介してきましたが、これらの豆知識を日常の会話やコミュニケーションで活用してこそ、真の価値が生まれます。子どもとの自然な対話から、大人同士の知的な雑談まで、タコの面白い生態は様々な場面で話題を盛り上げてくれる優秀な素材です。また、最新の研究情報を定期的にアップデートすることで、常に新鮮な知識を提供できるようになり、あなたの会話はより魅力的で豊かなものへと変化していくでしょう。
2024年・2025年の最新研究をチェックする習慣づくり
タコの生態研究は日々進歩しており、2024年から2025年にかけても新たな発見が続々と報告されています。最新情報を効率的に収集するには、いくつかの方法があります。まず、海洋生物学の専門機関や大学の研究発表をチェックすることです。日本では国立研究開発法人海洋研究開発機構(JAMSTEC)や各大学の海洋生物学科が定期的に研究成果を公開しています。また、科学雑誌のオンライン記事や、YouTubeなどの動画プラットフォームでも、最新の研究が分かりやすく解説されています。
私の場合は、月に一度、海洋研究機関のニュースレターを確認し、新しい発見があれば家族との食事の際に話題として紹介するようにしています。特に「タコの学習能力」や「問題解決能力」に関する研究は急速に発展しており、従来知られていた以上の知能を持つことが次々と明らかになっています。最新知識を会話に取り入れる際は、「最近の研究によると」という前置きを使うことで、聞き手の関心を引きつけることができます。また、タコの求愛行動や繁殖に関する新しい発見は、生き物の多様性について語る際の優れた話題となり、子どもから大人まで幅広い年齢層に興味を持ってもらえる内容として活用できるでしょう。定期的に情報をアップデートする習慣を身につけることで、あなたの知識は常に新鮮で信頼性の高いものになります。
次に水族館や料理店でタコに出会ったとき、見方が変わるはず
これまで学んだタコの雑学や生態の知識は、実際にタコと出会う場面で真価を発揮します。水族館でタコの展示を見る際には、単に「面白い生き物」として眺めるのではなく、その擬態能力や知能の高さ、複雑な行動パターンに注目することで、より深い観察体験を得ることができます。子どもと一緒に水族館を訪れた際に、「あのタコの腕には、それぞれに脳のような神経が集中しているんだよ」と説明すれば、子どもたちの驚きと興味を引き出すことができるでしょう。また、タコが岩に擬態している様子を見つけたときには、「わずか0.3秒で色を変えているんだよ」と伝えることで、その驚異的な能力をリアルタイムで実感できます。
料理店でタコ料理を注文した際にも、その生態についての豆知識は会話を豊かにしてくれます。「このタコはオスかな、メスかな。オスの方が身が締まっていて旨味が強いんだよ」といった話題は、食事の場を盛り上げます。また、タコの生息環境や食性について知っていれば、なぜタコが美味しいのか、どのような調理法が適しているのかといった話題へと自然に発展させることができます。「タコは貝やカニを食べているから、旨味成分が豊富なんだ」といった説明は、料理への興味をさらに深めます。多くの人が知らないタコの生態について語ることで、食事の場がより知的で楽しい時間となり、参加者全員の記憶に残る体験を提供できます。知識を持つことで、日常の何気ない場面が特別な学びの機会に変わるのです。
まずは1つ、明日使える豆知識から始めてみよう
この記事では数多くのタコの豆知識を紹介してきましたが、すべてを一度に覚える必要はありません。まずは1つ、自分が面白いと感じた豆知識を選んで、明日の会話で使ってみることから始めましょう。例えば、「タコには心臓が3つあって、泳ぐときは1つが止まるから長距離は苦手なんだ」という話は、子どもにも大人にも驚かれる話題です。あるいは、「タコの血液は青いんだよ。銅を使って酸素を運ぶからね」という豆知識も、科学的な興味を引き出す良い話題になります。
豆知識を効果的に伝えるコツは、押し付けがましくならないことです。自然な会話の流れの中で、「そういえば、こんなことを知ったんだけど」という形で話題を提供すると、相手も興味を持って聞いてくれます。相手の反応を見ながら、興味を示したらもう少し詳しく説明し、そうでなければさらっと流す柔軟さも大切です。また、「間違っているかもしれないけど」といった謙虚な前置きをすることで、会話がより自然になります。タコの豆知識は、子どもの好奇心を刺激し、大人の会話を盛り上げ、食事の時間を豊かにする、万能な話題です。まずは小さな一歩から始めて、徐々にレパートリーを増やしていくことで、あなたの会話はより魅力的で知的なものになっていくでしょう。タコという身近な生き物を通じて、科学への興味や生命への敬意を広げていきましょう。
この表でタコの驚くべき特徴がひと目でわかります。
| 特徴 | 詳細 | 豆知識 |
|---|---|---|
| 心臓の数 | 3個 | 泳ぐときは1個が止まる |
| 脳の構造 | 中央1個+腕に8個 | 腕が独立して判断可能 |
| 吸盤の数 | 1本の腕に約300個 | 味覚センサーの役割も |
| 寿命 | 1〜2年程度 | 交尾後は雌雄ともに死ぬ |
| 再生能力 | 腕の完全再生可能 | 約3ヶ月で元通りに |